剣道の試合に勝つための練習方法を考えよう

剣道を続ける理由は人それぞれあると思います。
段審査で上位の段を取得するため
健康のため
趣味としてやるため
私は剣道を通して、生徒が人間的に成長してくれることが何よりの喜びです。
しかし、剣道を続けていくためには
ある程度のモチベーションが必要です。
昨日までできなかった技ができるようになった。
今日は気持ちの良い一本が打てた。
先生に褒められた。
そんな小さなことでも生徒のモチベーションは変わってきます。
しかし、一番生徒のモチベーションが上がるのは、
試合に勝った時です。
試合に勝つことがすべてではありませんが、
一生懸命練習した成果が
一番わかりやすいのはここではないでしょうか。
一流の選手の話でも、試合で勝ったことが
剣道にのめり込んだ理由だと言っている方が多いように感じます。
たった2年半しかない中学校の部活生活で、
生徒には勝利の喜びを一度は味合わせたいと思っています。
ここでは、私が指導している練習方法の中でも、
試合に勝つために用意している練習メニュー
を紹介しています。
指導者の方、自分で練習方法を模索している方の
参考になればと思います。
基本を大切にしてきれいな剣道で勝つ
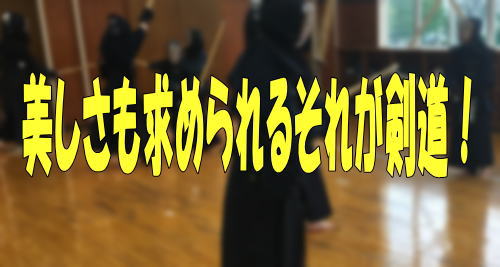
中学生の大会を見ていると、
フォームが汚かったり、
打つ間合いがめちゃくちゃだったりと
すごくクセのある剣道をする生徒の姿を見ます。
ではそういった子が勝てないかというと
そうではありません。
しかし剣道は試合の勝ち負けと同様、
美しさを求められる競技
だと考えています。
今は試合に勝てるからいいのかもしれませんが、
いつかはそのクセを直す日がやってきます。
ここでは試合に勝つだけではなく、
きれいな剣道で勝つことの大切さについて書いていきます。
手数の多い剣道の攻め

剣道をやっているとよく言われる
「もっと手数を増やしなさい」
という言葉。
手数を増やす=もっと打っていく
という風に考えがちですが、
闇雲にドンドン打っていっても、
剣道の上達にはつながりません。
私の考える「手数を増やす」というのは、
相手より先に打っていくのではなく、
がむしゃらに打っていくわけでもなく、
攻めていける状態をいつもでもつくり、
良いタイミングで必ず打っていくことです。
今回は足をすぐにつくる大切さと、
よけるのではなく、竹刀を払う感覚で、
手数を増やすことについて書いていきます。
緊張を味方につける
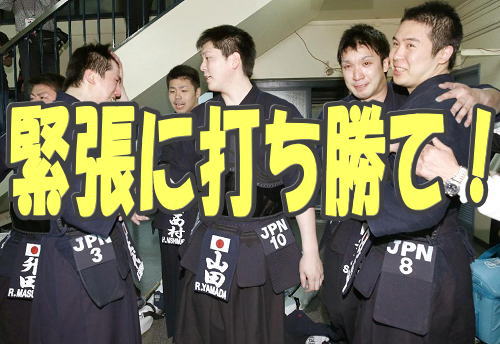
どんな競技でも大切だと言われるのが、
本番で100%の力を出せる精神力です。
精神力、つまりメンタルのことですね。
特に剣道という競技は、短い試合時間で、
相手を倒さなければならないという特徴があります。
少しの弱気、少しの迷い、少しの油断。
そういったことが、試合の結果を左右します。
こと中学生の剣道(特に女子)に関して言えば、
メンタルの違いで試合結果は簡単にひっくり返ります。
今回は剣道の試合の結果を左右すると言われる、
メンタルと、そのトレーニング方法を書いていきます。
相面で負けないようになる!
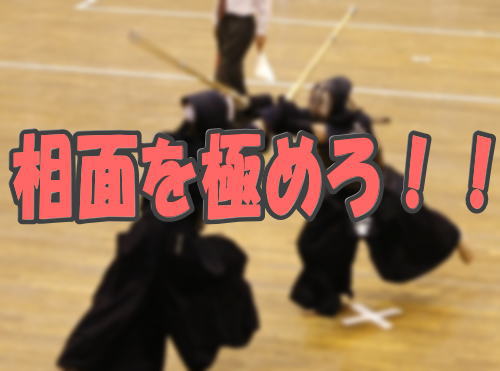
ある統計によると、全日本剣道選手権の
決まり技の80%は面だったそうです。
中学生の場合はもう少し低いかもしれませんが、
やはり一番多い決まり技は面だと思います。
その面の中でも決まる瞬間として多いのは、
相面であると私は感じています。
相面で絶対に負けない自信のある生徒は、
思い切って面を打つことが多いです。
以前関東大会まで進んだ時のメンバーの中に、
相面だけは絶対に負けない生徒がいました。
彼は相面で勝負できる場面を上手につくり、
1回の大会で5本相面を決めたことがありました。
恥ずかしながら、私も彼に相面では敵いませんでした(笑)
面が上手に打てるようになったら、
次にやることは、相面の打ち方を身に付けることです。
こうすることで試合の勝率はぐっと上がります。
ここでは試合で大活躍する相面について書いていきます。
出ゴテを打てるように!

剣道の試合を見ていて、
コテが決まるタイミングの多くは
出ゴテだと私は考えています。
試合中に、相手が面を打ってきたり、
手元をあげたりした瞬間にコテを打つ。
そういった場面での決まり技が出ゴテです。
私の学校のように初心者ばかりだと、
この出ゴテが中々うまく打てるようになりません。
今回は試合で使える出ゴテの打ち方について書いていきます。
生徒同士の掛かり稽古

剣道の稽古の中でも、きつい稽古はたくさんありますが、
その中でもかかり稽古はTOP3に入るきつい稽古だと思います。
「今から掛かり稽古やるぞ!」
そんな先生の言葉に、ゾッとする人も少なくないでしょう。
私自身も、かかり稽古のある稽古かどうかで、
体や心の疲れ具合が全く違いました。
掛かり稽古とは、まだ技を出すタイミングや、
攻め崩し方が分からない相手に対して、
そういったことを教えてやりながらやるものであり、
本来目上の先生に向かって、行うものだと私は思っています。
自分より強い相手に対して、積極的に打ち込んでいくことで
心を強くし、おかしな打ちやタイミングでは打てないことを学び、
技の出し方や、激しい連続打ちを知ることができれば最高です。
そうは言っても、実際には生徒同士で行うことが多いのが、
一般的な部活や道場の現状ではないでしょうか。
生徒同士でやった場合、ただ単に元立ちが
相手の打ち込み人形みたいになってしまっている、
掛かり稽古をよく目にします。
そういった掛かり稽古も悪くは無いのですが、
少なくとも元立ちは、せっかくの時間が無駄になってしまいます。
今回は私の考える効果的な掛かり稽古について
書いていきたいと思います。
チームの盛り上げ方!
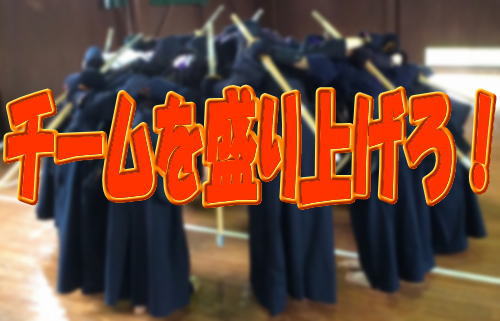
私は毎年、夏の全中へとつながる中体連の大会が近付くと、
夜に色々と考えてしまい寝られない日が続きます。
おそらく生徒以上に緊張しているのでしょう笑
大会前は選手も監督も緊張すると思いますが、
稽古中にはそれを吹き飛ばす雰囲気があるといいですよね。
大会前は、やはり部活が一丸となって、
良い雰囲気で盛り上がっていくのが理想だと思います。
しかし、どうも雰囲気が上がらない時もあるでしょう。
部活が全体的に元気がない。
緊張感が無くだらっとしている面が見られる。
大会前なのに本当にこれでいいのか?
そんな不安が余計に焦りに繋がり緊張になることもあるでしょう。
今回は、大会前のチームの盛り上げ方について書いていきます。
自分で審判をする
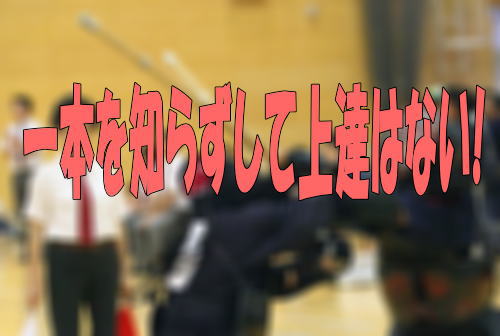
剣道の試合の勝敗を決めるのは審判です。
審判の一本の基準に達したとき、初めて旗が上がります。
私の学校の生徒には積極的に審判をやらせることにしています。
審判をやることで一本の基準を知り、
またどういう動きをすれば
一本になるのかを勉強できるからです。
ただ漠然と見取り稽古をする
何倍も効果的な練習方法だと思います。
ここでは審判をすることによって、
どのようなメリットがあるかを書いていきます。
打つべき機会タイミングを体感
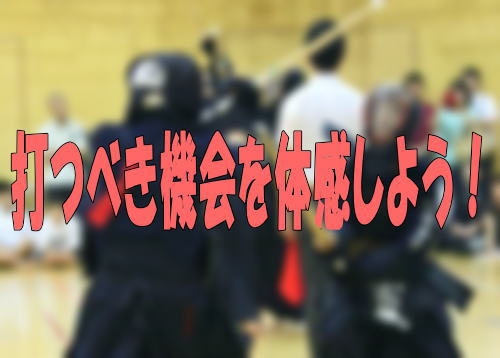
剣道の大切な要素に
打つべき機会を見つける
ことがあります。ただ闇雲に竹刀を振っていて
勝てるほど簡単なものではありません。
また、少々打突が軽かったとしても、
打つべき機会に打突できていれば一本になります。
ここでは剣道において大切な打つべき機会を
習得するための練習方法を紹介します。
Youtubeで試合観戦
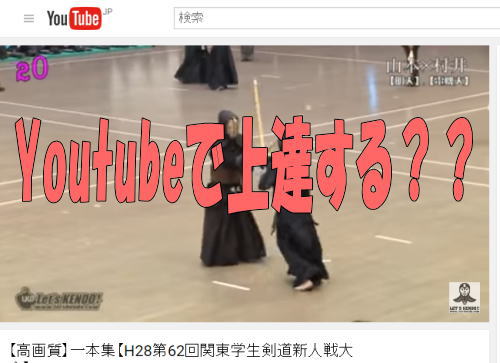
動画を利用して上達!
今は全日本選手権に大学生が出場したり、
高校生が日本代表チームに呼ばれたりと、
昔よりも若い選手の活躍が目立つようになりました。
私は、その理由の一つに、
Youtubeをはじめとした、
動画サイトの普及があると考えています。
私が学生のころは、試合を見る機会は、
実際に私自身が大会や練成会に行った時ぐらいしかありませんでした。
テレビで試合を見ようと思っても、
全日本選手権や玉竜旗くらいしかありませんでした。
しかし、今はPCやスマホがあれば、
簡単に上手な人の試合を見ることができます。
この動画での試合観戦が、剣道上達の秘訣になると
私は考えています。
中心をとった剣道
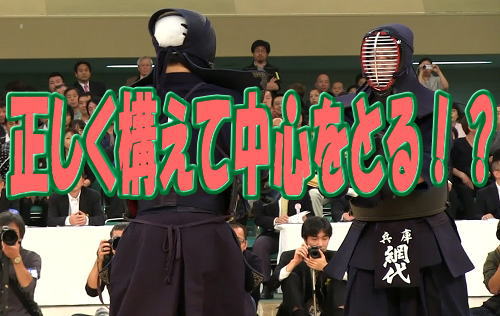
剣道においてよく言われる言葉
中心をとる
部活や道場で一度は指導されたことのある人も
多いのではないでしょうか?
私が剣道部の顧問になったばかりのころ、
この指導の大切さを理解していませんでした。
それどころか、他の中学校の先生が
中心をとる指導をしているのを見て、
なんでそんなことをいう必要があるのだろう?
という疑問すらありました。
私自身が選手時代にあまりそういった指導を
受けてこなかったことが大きな理由だと思いますが、
この中心をとるという話があまり
ピンときませんでした。
しかし、この中心をとるというということが、
最終的にはとても大切だということを
しばらくしてからようやく理解することができました。
ここでは剣道において大切な
中心をとるということについて書いていきます。
剣道の試合前・直前の稽古

試合前に緊張するのは、誰でも同じです。
それが最後の夏の大会であったり、
初めての試合であったりしたら、
なおさらだと思います。
私自身も教員大会に出場する時は、
かなり緊張します。
(もちろんあまり勝てませんが笑)
試合の2週間前くらいからは、かなり
試合を意識して練習に取り組むと思います。
さらに大会当日の練習。
いわゆるアップの仕方も考えなければなりません。
大会によっては時間や場所の関係で
できない場合もありますが、
ほとんどの大会では試合前に体を温める
アップの時間があると思います。
アップの様子を見ていると、
アップの仕方はチームによって様々です。
素振りだけで終わるところもあれば
面を付けて何度もかかり稽古を繰り返す
激しいアップをしているところもあります。
中にはアップしていないチームもありますが・・・。
もちろん素振りだけや
アップをしないようなチームは話になりません。
アップの時間を全く有効に使えていないと思います。
アップの様子を見ればそのチームの実力が分かる
と言っても過言ではありません。
審判を味方にする?みんなに応援してもらえる剣道部になる!

長いこと中学校の剣道部顧問をしていて、
応援してもらえるチームと応援してもらえないチーム
そういったチームを今まで見てきました。
優勝した時に「なんであんなチームが・・・」
と、思われてしまうチームと
「あのチームが優勝してくれてよかった!」
と、思ってもらえるチームが確かにあります。
どちらになりたいかと聞けば、どんな人でも
応援してもらえるチームがいい!
と、答えると思います。
剣道は人が審判をする競技です。
もちろん公平に審判をしているはずですし、
どちらかに肩入れをするようなことはあってはならないことです。
しかし、実力が拮抗しているギリギリの時に、
不思議と応援してもらえるチームの方が勝つことが多いです。
これは私が剣道部の顧問を続けてきた経験から言えることです。
応援できるチームになったほうが絶対に良い!
そんな話をここではしていきたいと思います。
